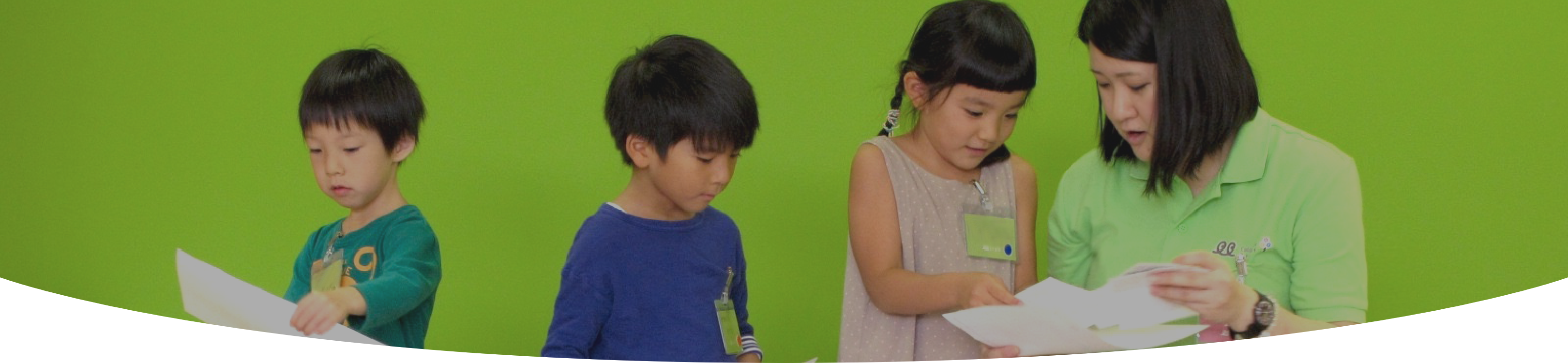
お知らせ
News

発達障害の子とプログラミング教育:適性よりも学び方の選択肢を広げる【東京都港区不登校フリースクール】
1. 「発達障害の子はプログラミングに向いている」という誤解
近年、「発達障害の子どもはプログラミングに向いている」といった言説を目にすることがあります。しかし、この考え方には慎重になる必要があります。
プログラミングを学ぶ本質的な要素には、他者との協力やコミュニケーションが含まれています。プログラムを書くこと自体は一人で行うことも可能ですが、実際の開発現場ではチームでの作業が求められることがほとんどです。そのため、「発達障害の子どもがプログラミングに向いている」というのは、一概に正しいとは言えません。
しかし、発達障害のある子どもたちの中には、学校の座学よりも、プログラミングの学び方の方が合っているというケースが多くあります。
2. 学校の学びが合わない子どもにとってのプログラミング
発達障害の特性は一人ひとり異なりますが、
- 言語的な説明よりも、視覚的な学習の方が理解しやすい
- 細かい作業やパターンを繰り返すことが得意
- 興味のある分野には強い集中力を発揮できる
といった傾向を持つ子どもにとって、プログラミングは「自分のペースで学べる」点が魅力となることがあります。
学校の一斉授業では、すべての子どもが同じペースで学ぶことを求められます。しかし、プログラミングの学習は、
- 自分で試行錯誤しながら進められる
- 失敗してもやり直しができる
- 「正解」が一つではなく、自分なりのアプローチができる
といった特徴があり、これが発達障害の子どもたちにとって学びやすい環境を作り出します。
3. 体験的な学びの重要性
発達障害の子どもたちにとって、「体験を通じた学び」が重要です。学校の座学では集中しづらい子どもでも、
- 実際に手を動かしてプログラムを組む
- ロボットやゲームを作りながら試行錯誤する
- インタラクティブな学習ツールを活用する
といった環境であれば、楽しく学べる可能性が高くなります。
例えば、視覚的なプログラミング環境である「Scratch」や、ロボットを使ったプログラミング学習では、直感的な操作が可能であり、文字情報よりもイメージで理解しやすい学び方ができます。
また、発達障害のある子どもにとって、興味のあることを追求できる環境はとても大切です。プログラミングは、決められたカリキュラムをこなすだけでなく、自分が「やりたい」と思ったことを形にすることができる点で、非常に魅力的な学びの手段となり得ます。
4. 学びの多様性を広げるために
発達障害の子どもがプログラミングを学ぶことは、「向いているから」ではなく、「学び方が合っている可能性があるから」です。
そして、この視点は発達障害に限らず、すべての子どもに共通する重要なポイントです。学校の授業だけでは合わない子どもたちが、自分に合った学びのスタイルを見つけられる環境を作ることが大切です。
- 一斉授業だけではなく、個別での学習機会を増やす
- 視覚的・体験的な学びを重視する
- 興味のあることを自由に探求できる環境を提供する
こうした学びの多様性を広げることが、教育全体の課題でもあります。
5. まとめ:プログラミングは「適性」よりも「学びの選択肢」
発達障害の子どもがプログラミングに向いているのではなく、プログラミングの学び方が、学校の学習スタイルよりも合っていることがあるという視点が重要です。
学びの方法は一つではありません。学校の一斉授業が合わない子どもにとって、プログラミングを含めた体験的な学びが新しい可能性を開くことがあります。
子ども一人ひとりの特性に合った学びの場を提供することこそが、これからの教育の課題であり、私たちが大切にすべきポイントなのです。
【関連記事】
お問い合わせ
🌍アクセス🌍
移転先の南青山教室でイベントを行います!
東京都港区南青山1丁目15-40 ウィステリア南青山1階
⚫︎『青山一丁目駅』から徒歩6分程度
⚫︎『乃木坂駅』から徒歩6分程度
⚫︎専用の駐車場・駐輪場はありません。お車や自転車でお越しの方は、お近くのパーキング等をご利用ください。

💌お問い合わせはLINEから!
公式LINEから個別メッセージでのお問い合わせも可能です。
ご不明点やご質問などお気軽にお送りください✨
株式会社コトイズム
〒106-0032 東京都港区六本木4−1−4 黒崎ビル2階
電話:050-1720-0361
メール:info@kids-mirai.jp

