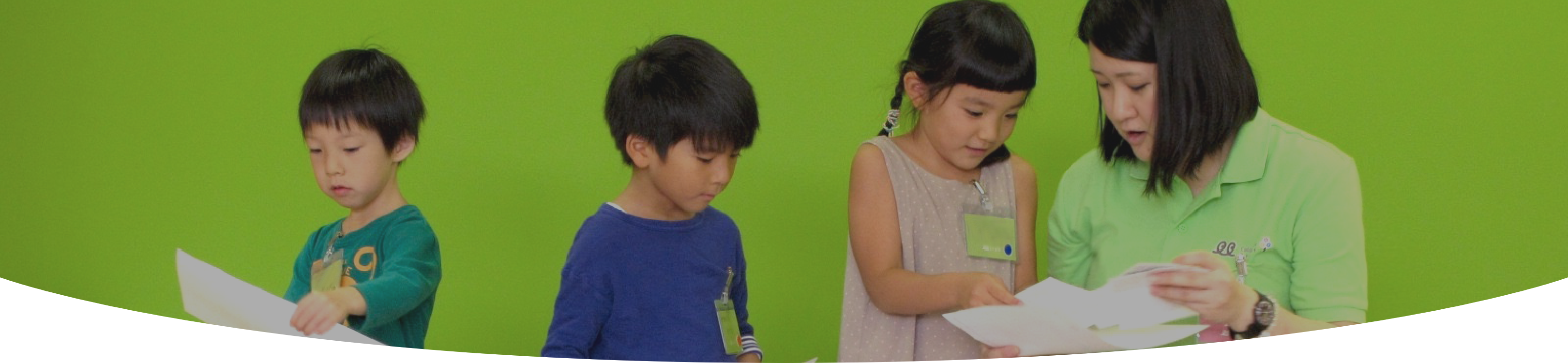
お知らせ
News

マイクラカップ歴代テーマから見る教育的可能性と子どもたちの学び
マイクラカップのテーマ設定における教育理念
マイクラカップは、2019年の第1回大会から一貫して、子どもたちが現代社会の課題に向き合い、未来を創造する力を育むことを目的としてきました。各回のテーマは、単なるゲーム課題ではなく、深い教育的意図を持って設計されており、子どもたちの21世紀型スキル習得を促進する重要な役割を果たしています。
大会運営委員会ディレクターの土井隆氏は「実際に未来を創造していくのは子どもたちですし、それを自由に表現できるのがマインクラフトの強みだと思っています。そこで、未来志向になるようなSDGsのテーマを毎年検討しています」と述べており、テーマ設定の背景にある教育哲学が明確に示されています。
第1回(2019年):スポーツと地域コミュニティ
テーマ:「スポーツ施設のある僕・私の街~ワクワクする「まち」をデザインしよう〜」
記念すべき第1回大会では、スポーツを軸とした地域コミュニティの創造をテーマに設定されました。このテーマの教育的価値は以下の点にあります:
社会包摂の概念理解 子どもたちは「どれほど多様な人々が充実した暮らしができるか」という評価基準を通じて、バリアフリーやユニバーサルデザインの重要性を自然に学習しました。スタジアムや運動場、体育館などの施設設計において、年齢、性別、身体能力の違いを超えて、全ての人が楽しめる空間づくりを模索する過程で、社会包摂の概念を体感的に理解することができました。
地域活性化への理解 スポーツ施設を中心とした街づくりを通じて、地域経済や観光、住民の健康促進など、多角的な視点から地域活性化について考える機会を提供しました。133チームがエントリーし、子どもたちは自分たちの住む地域の特性を活かした独創的な街づくりに挑戦しました。
第2回(2020年):未来の教育とSociety5.0
テーマ:「未来の学校~ひとりひとりが可能性に挑戦できる場所~」
コロナ禍という社会情勢を受けて設定されたこのテーマは、教育の在り方そのものを問い直す深い内容でした。
教育DXの先駆的思考 2020年当時、オンライン教育が急速に普及する中、子どもたちは未来の学校像を自由に構想しました。最優秀賞を受賞した浦添昴さんの作品「未来への5つの約束〜キレイな水と渓谷の洞窟学校」は、食・エネルギー・環境・まちづくり・教育の統合的な解決策を提示し、持続可能な学習環境のビジョンを示しました。
個別最適化学習の模索 「ひとりひとりが可能性に挑戦できる場所」というサブテーマは、現在の教育改革で重視されている個別最適化学習の概念を先取りしており、子どもたち自身が学習者の多様性を尊重する教育環境をデザインする機会となりました。
第3回(2021年):SDGs時代の住環境
テーマ:「SDGs時代のみんなの家、未来のまち」
第3回大会から本格的にSDGsとの連携が明確化され、持続可能な社会づくりが主要テーマとなりました。
重点目標と具体的学習
- 目標3「すべての人に健康と福祉を」:バリアフリー住宅やヘルスケア施設の設計
- 目標7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」:再生可能エネルギーシステムの理解
- 目標15「陸の豊かさも守ろう」:生態系保全を考慮した都市計画
協働学習の実践 大賞を受賞したチーム「7人のクラフター」は、コロナ禍で一度も対面で会うことなく作品を完成させました。SNSを活用したコミュニケーション、役割分担、ルールづくりなど、デジタル時代の協働スキルを実践的に学習しました。特に注目すべきは、バイオガス発電所の採用理由として「動植物に与える影響が少なく、発電時に出る排水を街の畑に再利用できる」という環境配慮の視点を示したことです。
第4回(2022年):生物多様性と持続可能性
テーマ:「生き物と人と自然がつながる家・まち~生物多様性を守ろう~」
積水ハウスがパートナーとして参画し、住宅産業の観点から生物多様性保全を考える機会を提供しました。
生態系サービスの理解 子どもたちは「生き物たちの豊かな個性とつながり」について学び、人間の生活が自然界の恩恵によって支えられていることを理解しました。積水ハウスの「5本の樹」計画(3本は鳥のために、2本は蝶のために)のような企業の環境取り組みを学習し、実際の街づくりに反映させることで、ビジネスと環境保全の両立について考える機会を得ました。
重点目標の深化
- 目標14「海の豊かさを守ろう」:海洋生態系保全の重要性
- 目標15「陸の豊かさも守ろう」:森林保全と都市緑化の統合
ジュニア部門最優秀賞のCCさんの作品「空飛ぶ雷さまの方舟」は、自然災害から生き物を守る発想と、生物多様性保全を組み合わせた独創的なアプローチを示しました。
第5回(2023年):持続可能な社会の実現
テーマ:社会課題解決に向けた持続可能な街づくり
10,350人がエントリーし、500作品が集まったこの回では、SDGs目標5、7、11の中から1つ以上を選択し、目標達成に向けたアイデアをマインクラフトで表現することが求められました。
重点目標による専門性の深化
- 目標5「ジェンダー平等を実現しよう」:多様性を尊重する社会システム
- 目標7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」:持続可能なエネルギー社会
- 目標11「住み続けるまちづくりを」:包摂的で持続可能な都市開発
調査研究活動の重視 この回から、作品制作のための現地調査が重視されるようになりました。発電所への見学、地域施設へのインタビューなど、実際の社会課題を肌で感じる体験を通じて、より現実的で実効性のある解決策を模索する姿勢が評価されました。
第6回(2024年):Beyond SDGs – Well-being社会
テーマ:Well-being(ウェルビーイング)な未来社会の実現
「Beyond SDGs」という概念を導入し、SDGs達成後の理想的な社会状態であるWell-beingを追求するテーマが設定されました。
Well-beingの多面的理解 Well-beingを「みんなが心地よい暮らしを送り、楽しさや安心感を感じ、”幸せ”に過ごすこと」と定義し、子どもたちは物質的な豊かさを超えた精神的な充実や社会的なつながりの重要性について考察しました。
万博テーマとの連携 たてもの部門では「未来の技術でパビリオンを創造しよう」として、2025年大阪・関西万博と連携した課題設定が行われました。これにより、子どもたちは国際的なイベントと社会課題解決の関係性について理解を深めることができました。
第7回(2025年):レジリエンスと危機管理
テーマ:「未曽有の災害から人類の命を守れ!~レジリエンスを備えたまちづくり~」
現在進行中の第7回大会では、自然災害や紛争など、現実的な危機に対応できる社会システムの構築がテーマとなっています。
レジリエンス概念の教育価値 「辛い状況の中でも、人々は『立ち上がる力』を持っています。それが『レジリエンス』です」という定義を通じて、子どもたちは危機に対する社会の適応能力について学習します。大変な出来事があっても人々が支え合い、より強く安全な形で復旧・復興する力を持った街やたてものをデザインすることで、防災・減災の重要性を体感的に理解できます。
CotoMiraiにおけるテーマ学習の実践
段階的な理解促進
港区南青山のプログラミングスクールCotoMiraiでは、これらの歴代テーマを活用した学習プログラムを提供しています。
幼児期からの社会課題への関心育成 3歳から参加できる「プログラミングトイスポット」では、遊びを通じて社会の仕組みへの関心を育み、年中から始まるスクール利用では、マイクラカップのテーマを通じて具体的な社会課題について考える機会を提供しています。
個別最適化された学習支援 1人1人の興味関心、年齢や能力に合わせたゴール設定により、各回のテーマから子どもの発達段階に適した学習要素を抽出し、段階的な理解を促進します。
探求心・ことば・情報活用の統合的育成
- 探求心:歴代テーマへの夢中な取り組みを通じて、社会課題への関心を深化
- ことば:作品のプレゼンテーションを通じて、自分の考えを論理的に表現する力を育成
- 情報活用:テーマに関する調査研究活動を通じて、問題発見・解決能力を養成
教育的可能性の多面的展開
認知能力の向上
批判的思考力の育成 各テーマは単純な答えのない複雑な社会課題を扱っているため、子どもたちは多角的な視点から問題を分析し、最適解を模索する批判的思考力を身につけます。
創造的問題解決能力 マインクラフトの制約の中で理想的な社会システムを構築する過程で、既存の枠組みにとらわれない創造的な発想力が育成されます。
社会情緒的学習(SEL)
共感性と多様性理解 各テーマが「全ての人々」「多様な生き物」「様々な立場の人」を考慮した設計を求めることで、他者への共感性と多様性を尊重する態度が自然に育まれます。
責任感と社会貢献意識 自分たちの作品が社会課題の解決に寄与するという意識を通じて、社会の一員としての責任感と貢献意識が醸成されます。
メタ認知能力の発達
学習プロセスの振り返り 作品制作の計画立案から完成まで、そしてプレゼンテーションに至るまでの一連のプロセスを通じて、自分の学習方法や思考過程を客観視するメタ認知能力が発達します。
未来社会を担う力の育成
グローバル市民性の育成
歴代テーマを通じて、子どもたちは地球規模の課題を自分事として捉え、国際的な協力の重要性を理解します。SDGsという国際的な枠組みを学習の軸とすることで、自然にグローバル市民としての意識が育まれます。
イノベーション創出能力
技術(マインクラフト)と社会課題を組み合わせた課題設定により、デジタル技術を社会課題解決に活用するイノベーション創出能力が養われます。これは、Society5.0時代に求められる重要なスキルです。
持続可能な思考の習慣化
毎年異なる角度から持続可能性について考える機会により、短期的な解決策ではなく、長期的視点で物事を考える思考習慣が身につきます。
保護者と教育者への示唆
家庭学習への活用方法
日常会話での深化 マイクラカップのテーマは、家庭での日常会話にも活用できます。ニュースで自然災害が報じられた際に「レジリエンスのある街ってどんな街だと思う?」といった問いかけを通じて、子どもの思考を深めることができます。
地域探索活動の促進 各テーマに関連した地域の施設見学や関係者へのインタビューなど、実体験を通じた学習を家庭でも実践することで、より深い理解につながります。
学校教育との連携可能性
教科横断的学習の実現
- 社会科:各テーマに関連した社会制度や歴史的背景の学習
- 理科:再生可能エネルギーや生態系に関する科学的理解
- 国語:調査結果のまとめやプレゼンテーション技術の向上
- 算数・数学:統計データの分析や設計における計算技術
まとめ:継続的な学びの重要性
マイクラカップの歴代テーマは、単年度の学習課題ではなく、子どもたちの成長に伴って段階的に深化していく継続的な学習機会として設計されています。幼児期からの参加により、社会課題への関心が自然に育まれ、小学校高学年から中学生にかけて具体的な解決策を模索する力が身につき、高校生では実現可能な政策提言レベルまで思考が発達します。
CotoMiraiでは、これらの教育的価値を最大限に活用したカリキュラムを提供し、子どもたちの「やってみたい・つくってみたい」という内発的動機を大切にしながら、未来社会を担う力を育成しています。
お子様の未来への投資をお考えの保護者の皆様へ
マイクラカップの歴代テーマが示すように、現代の子どもたちには、単なる知識の習得を超えた、複雑な社会課題に向き合う力が求められています。CotoMiraiでは、3歳からの段階的なプログラミング教育を通じて、これらの21世紀型スキルを楽しみながら身につけることができます。
まずは無料体験会で、お子様がマイクラカップのテーマにどのように向き合うかを体験してみませんか?LINE公式アカウントから気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ・無料体験のお申し込み CotoMirai公式サイト:https://kids-mirai.jp/ 未来を創る力を、今から一緒に育てていきましょう。

